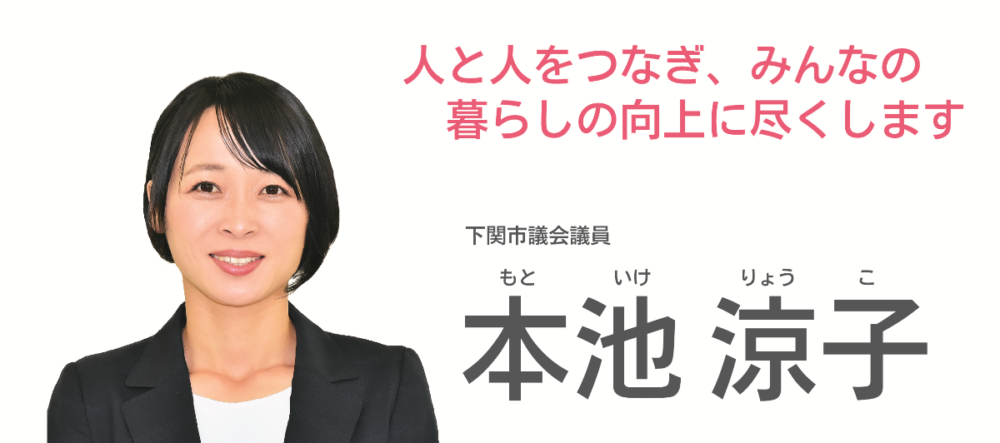下関市議会2月定例会が終わりました。
今回の個人質問では、下関市内の学校校舎がボロボロのまま放置され、子どもたちが危険な状況で学ばなければいけない状況になっていることについて質問しました。さらに、築60~70年を経過した老朽校舎を「長寿命化」によって築100年まで使うという計画も進められています。巨額なハコモノ事業が矢継ぎ早に決まっていく一方で、他市と比べてもあまりにひどい子どもたちの教育環境の現状と今後について、市はどのように考えているのか――。
以下は、私がおこなった個人質問の質疑要旨です。後半では、私の質問に対して前田市長が憤慨される場面もありましたが、こちらが指摘していることとのずれを感じました。その熱量は子どもたちの教育環境改善のために注いでもらいたいと思います。ぜひみなさまのご意見をお聞かせください。

本池 子どもたちが育つ教育・保育環境の維持管理、改修、更新について質問する。この度の予算案は市長選の関係で主に義務的経費や継続事業が計上される骨格予算となっている。であるからこそ、日々必要となる予算が、必要なところに必要なボリュームで宛てられているかどうかを見ることが大事だと思っている。
なかでも今回、下関の将来を担っていく大切な子どもたちが、健やかに、安全に育つ環境になっているか、子育て世代が安心して子どもを預けることのできる施設状況が整っているのか、不具合が生じた場合、適宜改善できる予算が計上されているか。予算議会とは全体の予算の配分を審議するものである。教育費については今年度と比較し10億円の増額となっているが、これが適切な配分であるのか、質問する。
まずはじめに小・中学校の現状について、今、学校関係者、保護者のなかで小・中学校の校舎やその他の学校施設の老朽化が非常に問題にされている。

これは校舎の外壁だ【上、写真】。老朽化した外壁の剥落が起きているため、教育委員会の方が来て危険な箇所を叩き落としているが、ご覧のような状況だ。これが市内各所にある。そして渡り廊下の屋根は、ボロボロになって穴が開いている。
 2枚目は上下とも雨漏りの写真【上、写真】だが、上の写真は屋上のドアの隙間やこの穴から雨が入り込んできて、階段が滝のようになる。下の方は天井が抜いてあり雨漏りの水を受けるバケツが置かれている。3枚目は以前私も一般質問で取り上げたこともあるが、使用禁止のトイレだ【下、写真】。すぐに流せず時間がたてば水が流れてくる「配タンク式」のため、臭いもしやすい。
2枚目は上下とも雨漏りの写真【上、写真】だが、上の写真は屋上のドアの隙間やこの穴から雨が入り込んできて、階段が滝のようになる。下の方は天井が抜いてあり雨漏りの水を受けるバケツが置かれている。3枚目は以前私も一般質問で取り上げたこともあるが、使用禁止のトイレだ【下、写真】。すぐに流せず時間がたてば水が流れてくる「配タンク式」のため、臭いもしやすい。
 今紹介した写真のなかにはすでに改善に向けて進み始めているものも含まれているが、ご覧のとおりあちこちボロボロだ。しかもそれが長期間にわたって放置されていることから、保護者や教育関係者から怒りの声が上がるのも当然だ。
今紹介した写真のなかにはすでに改善に向けて進み始めているものも含まれているが、ご覧のとおりあちこちボロボロだ。しかもそれが長期間にわたって放置されていることから、保護者や教育関係者から怒りの声が上がるのも当然だ。
学校施設の維持・管理については現在、「下関市学校施設長寿命化計画」にもとづき、修繕・工事を実施している。しかしながら、これまで何十年もまともに維持・管理がおこなわれてこなかったため、多くの学校ですでに危険な状態になっている部分も多く、校舎をはじめとした施設の改修・更新が待ったなしの状況だ。他市を経験してこられる先生方、教育委員会関係のみなさんも「下関市の学校施設の古さは異常だ」と話題にしている。
日々学校に通う児童・生徒のために、もっと大々的に、短期間での対策が必要であり、修繕にとどまらず、将来を見据えた思い切った建て替えも必要であると感じている。まず、長寿命化計画による学校施設の維持・管理について、これまでのとりくみを答えてほしい。
藤田教育部長 令和2年度に「下関市学校施設長寿命化計画」を策定し、その後、対象施設等の見直しにともない、令和5年度に改訂した。長寿命化計画にもとづき、学校施設の維持管理を計画的に実施してきているところだ。学校施設の長寿命化のための大規模改修から、外壁落下防止のための外壁改修、漏水対策のための屋上防水改修、水道、電気、ガス管等のライフラインやそれらに関する設備機器類の予防保全、老朽状況等に応じ対応している。
本池 「長寿命化計画にもとづき対応している」といわれたが、先ほど紹介したようにボロボロの状況が長期にわたっていて、今も改修の目途がないものが多くあり、「対応」とはなんなのか考えさせられる。とくに、校内の雨漏りなどは、場所の特定もできずお手上げ状態といわれている。確かに「計画的に進めている」と思うが、対応できているとはいえず、するのであれば劇的に改善する予算を付けなければならない。今の学校施設の置かれている現状を受け、教育委員会としては今後の施設改修の進め方をどのように考えているのか。
藤田教育部長 今後も引き続き、長寿命化計画に基づいて学校施設の適切な維持管理を計画的に実施していきたいと考えている。大規模改修にかかわらず、外壁落下防止等の必要な改修については、その時々に合わせて児童の安全のために計画的に実施していきたい。
本池 あくまでも長寿命化計画にもとづき進めていくということだが、長寿命化計画は、閉校時期が決まっている学校を除き、小・中学校合わせて60校の校舎、体育館、武道場、給食室の254棟が対象となっている。次の図【図1、下】がこの254棟の「築年別整備状況」だが、下関市の場合254棟のうち昭和36年以前に建設された校舎が圧倒的に多いことが分かる。長寿命化に向けて構造躯体の調査をおこない、判定の結果、長寿命化する建物は237棟もある。
 現在、長寿命化改良が進んでいる勝山中学校では3棟の改修がおこなわれており、その期間は今後も含めて7年。残る234棟すべてが完了するのに何年かかるのか。
現在、長寿命化改良が進んでいる勝山中学校では3棟の改修がおこなわれており、その期間は今後も含めて7年。残る234棟すべてが完了するのに何年かかるのか。
この計画には校舎の「目標使用年数」がある。現状の建物の耐用年数は鉄筋コンクリートの場合47年とされているが、長寿命化することで目標使用年数を100年にするという。たった今、今後もこの長寿命化計画にもとづいてやっていくと答えられたが、現場感覚としては100年使うなんてとんでもない話で、早急な改善が求められている。本当に今の校舎群を100年使おうと思っているのか。
藤田教育部長 現在ある建物を今後も長期的に使用する場合の判断として、構造躯体が健全であることが確認できた建物については、必要な改修を実施して引き続き使用したいと考えている。使用できる建物に対して必要な改修をおこない、使用し続けることで総事業費の縮減にも繋がると考えている。文科省においても、平成27年に「インフラ長寿命化計画」を策定し、施設の長寿命化に向けたとりくみを推進しているところだ。ただ一方で、今後、教室の広さや、学習環境に必要な設(しつら)えの変更、また建物構造や安全面の基準等、構造躯体に大きな変更が必要となった場合には、建て替えも視野に入れ検討したい。
本池 今の計画では、構造躯体が健全である建物については改修をして100年使うということか。
藤田教育部長 国の方針もあり、利活用できるものは利活用していく。この計画そのものが事業費の縮減、コストの平準化というのもあり、それらも睨みながら利活用できるものは活用していく。
本池 長寿命化については前提条件があるのだと理解している。確かに国も「100年使える」といっているが、それは適切な管理をしている場合の話ではないだろうか。実際、計画にも「今後は建築後40年を経過するころに改修を実施し、建築後100年まで使用できるよう建物の長寿命化をはかります」とある。
先ほど確認したとおり、下関市の場合50~70年以上たっている校舎が多くある。そしてこれらは「40年を経過するころ」に改修を実施していないどころか、普段の維持・管理もままならず、壊れたり不具合が発生して初めて対応することで現在まできているため、老朽化が深刻になっているのだ。だから、この計画にあるように本当に100年持たせるつもりなのかと聞いている。
そしてみなさん思い出してほしいが、この市役所本庁舎は築59年で建て替えている。建設当時の素材や施工が良かったのか、コンクリートの劣化もさほど進行していないという検査結果も出ていたが新たに建て替えることになった。だったらそれよりも深刻な劣化状況に直面している施設、子どもたちが日々過ごしている学校施設の建て替えの心配をしてほしいし、大人の責任で建て替えてあげなければならないのではないか。市役所だけ建て替えて、子どもたちの使う学校は「躯体が健全だから使えるうちは使う」などあまりにも冷たい。
「建て替えも含めて検討する」といったじゃないかと思われるかもしれないが、今、教育委員会がいっている「建て替え」は、国の施策や方針に対応するためのものでしかなく、下関の置かれている現実からみたボロボロの校舎を早急に改善するための校舎の建て替えは進まない。
20億円かけて大規模改修 なぜ建て替えない?
本池 長寿命化事業のとりくみ内容は「大規模改修」と「予防保全」だ。100年もたせるための大規模改修をおこなっているのが勝山中学校で、令和7年度予算も引き続き勝山中学校の大規模改修にかかる経費が計上されている。勝山中学校の次の大規模改修の計画はあるのか。優先順位第2位となっている川中小学校に着手する見通しはあるのか。
藤田教育部長 勝山中学校においては、構造躯体の劣化部分の改修や建物の内部・外部改修のほか、水道・電気・ガス管等のライフラインの更新など、施設を今後も長期間使用するために必要となる全面的な改修工事、いわゆる長寿命化工事を実施している。その他の学校施設の長寿命化については、勝山中学校の事業実施について十分な効果検証をおこなうとともに、対象とする学校における事業期間中の児童・生徒への影響をはじめ、建物個々の劣化状況等に応じて、実施する工事の手法や工事をおこなうための仮設校舎などの設置、事業期間、事業費を精査し、計画的に進める必要があると考えている。
本池 勝山中学校の事業について検証するということだ。勝山中学校1校の大規模改修では事業期間が7年、事業費総額は約20億円になった。20億円もあれば建て替えもできたのではないかとの意見も聞こえてくるし、検証も「今のペースで、この金額でいいのか」という評価があるからだと思う。勝山中学校を建て替えた場合の試算はされているのか。
藤田教育部長 勝山中学校の長寿命化に着手するさい、校舎を建て替えた場合の試算はしていない。長寿命化計画の策定にあたり、建物の老朽度の実態について、構造躯体の健全度や構造躯体以外の劣化状況を調査した。その結果として構造躯体は健全であることが確認できたことから、建て替えではなく、既存建物の長寿命化を選択したために、建て替えた場合の試算はしていない。
本池 建て替えの試算はしていないということだ。
勝山中学校1校で約20億円。いま建築後50年程度だからこの金額をかけてあと50年持たせるということだ。一方で、建て替えの試算はされていないということなので私も少し調べてみたが、学校を新築した場合、1平方㍍あたりの単価がおよそ40万円。勝山中学校の面積で計算した場合、約22億円になる。解体費等は入っていないので、そうした部分の増額はあるが、20億円かけて50年延長させるのと、同規模の額で新築し、適切な維持・管理をしながらなるべく長く使う、なにより今のボロボロの環境を一気に改善できる、このどちらが費用対効果としていいだろうか。
これも机上の計算なのでわからないが、なにがいいたいかというと「国がやれといっているから」と下関の実情を無視して、長寿命化という「結論ありき」で無理やりやっていても誰のためにもならないということだ。

人口が増えた校区ではそもそも学校の教室が不足している
本池 現実的なコスト比較はしていないということで、実際になにをもって「長寿命化のほうがいい」と判断したのかというと、長寿命化計画に「コスト試算」というものがある。平たくいうと、50年間で改築、20年で事後修繕的な改修をおこなう「従来型」と、概ね40年で長寿命化をおこない100年たって改築をおこなうなどの「長寿命型」で比較した場合、結論として「従来型に比べ、整備費用を40年間の総額288億円(年間7・2億円)縮減することができる」「目標使用年数を100年とすることで、長寿命化や大規模改造(予防保全)を長期間で実施することが可能となり、40年間の総額及び年度整備費を可能な限り低減することができる」としている。
これは文科省のソフトではじき出されるもので、長寿命化が可能とされたものについては建て替えより長寿命化のほうが整備費の低減と平準化ができるということのようだが、このなかに次のような記載がある。「なお、実際の本市における学校施設の維持管理は、これまでに計画的な大規模改造等はほとんど実施しておらず事後修繕で対応していますが、試算上は過去に計画的に大規模改造等を実施しているものとみなして、今後必要となるコストを試算します」。
これを聞いてどう思われるか。長寿命化計画のなかでも「学校施設の実態」の部分は現状を反映した貴重な資料だと思う。ただ下関の場合、これまでほぼ改修を施していないので、その後の「方針」の部分があまりにも現実にあっていない。一般的に公共施設の長寿命化というのは、それまでに維持・管理をしっかりと施していることが前提になるが、その前提条件はないのに、「長寿命化」だけが一人歩きしているように思えてならない。
これまでほとんど手を入れてこなかった下関市の学校施設が「長寿命化」に馴染むのかが不明であり、コスト的に優位なのかも不明だ。なにより問題なのは、「長寿命化して使う」という方針決定をしたがために、教育環境がいつまでたっても改善されない。せっかくつくった計画ではあるが、「絵に描いた餅」になってしまっているのが現状ではないか。
ついでにいうと教育委員会の長寿命化計画は、総務部の公マネの「施設用途別方針」が上位計画になっているため、どれだけ学校がボロボロでも建て替え計画が出てくるわけがない。いつまでもいつまでも、児童数の計算ばかりしている。来年度におこなう長寿命化計画の見直しにあたっては、実態を改善するためにどうするのかという方向で、教育委員会だけでなく全庁的な議論をしっかりとしていただきたい。
104棟が「早急な対応が必要」な外壁 来年度の修繕予定は2校のみ?
本池 話を長寿命化事業「予防保全」に切り替える。長寿命化計画において、構造躯体以外の部分については、「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「機械設備」「電気設備」の5項目についてA~Dの4段階で評価がされている。そしてその結果が次のようになっている。
 とくに「屋上」と「外壁」については4割以上が「D=早急な対応が必要」となっている。大規模改修の順番がいつまでも回ってこないなかで、外壁の剥落、雨漏り、内装の劣化、故障したり悪臭漂うトイレ、体育館、給食室への早急な対応が必要となっている。これらの維持・管理にはどのように対応していくのか。
とくに「屋上」と「外壁」については4割以上が「D=早急な対応が必要」となっている。大規模改修の順番がいつまでも回ってこないなかで、外壁の剥落、雨漏り、内装の劣化、故障したり悪臭漂うトイレ、体育館、給食室への早急な対応が必要となっている。これらの維持・管理にはどのように対応していくのか。
藤田教育部長 議員の方から大規模改修をしていないという話があったが、長寿命化計画にかかわらず、これまでも外壁改修や屋根の防水などその時々で対応してきている。大規模的なものはできていないところもあるが、そこは時々の状況でやってきているので、その点はのべさせていただきたい。
長寿命化計画では、建物の種別ごとに、児童生徒がより多くの時間を過ごす場所を優先するために、校舎、屋内運動場、武道場、給食室等その他の施設の順に改修を実施することとしている。しかしながら、学校施設の維持管理にあたっては、児童生徒の安全を最優先に対応するために、建物の種別ごとの優先順位にとらわれず外壁落下防止のための外壁改修工事や、漏水対策のための屋上防水改修工事等、個別に必要な工事を実施しているところだ。また、児童生徒の学習環境や生活環境を整えるために、学校トイレ快適化事業やトイレ洋便器化については、長寿命化改修工事とは別に先行して実施している。
本池 生徒の安全のための予防保全について、来年度予算では3億5150万円がついている。これ自体はここ数年で増額となっている。しかし、ただ「予算をつけた」だけでなく、そもそもの予算が足りているのか、改善されているのかという点が大事だ。躯体以外の部分の劣化状況について、例えば、外壁については計画で254棟中104棟が「早急な対応が必要」で「5年以内の修繕を必要としている」となっている。なのに、来年度予算では2校分と聞いた。2校分でいいのか。それで5年以内に残りの100棟近い校舎の外壁修繕は終わるのか。見通しを聞かせてほしい。
藤田教育部長 安全面に配慮し、状況に応じて必要であれば改めて検討する必要もあると考えているので、児童・生徒の安全のために措置はとっていきたい。
本池 トイレの話が出たのでトイレ快適化事業とトイレの洋式化について聞くが、令和3年度から実施されているトイレ快適化事業で、改修が必要とされたのは全体で何フロアで、何フロアが改修できたか。
藤田教育部長 学校トイレ快適化事業の対象箇所としては、令和3年度の事業着手時点で42校249フロアだ。工事の概要としては、和式便器の洋式化、床面の乾式化、段差の解消など全面改修する計画になっている。
ただし学校トイレ快適化事業は長期的な計画であるため、別途、児童生徒の教育環境改善のため、和便器の洋式化を進めており、令和3年度から令和5年度までに9校29フロアを整備した。令和6年度の工事完了見込みを含めると、12校37フロアになる。トイレの洋式化については平成29年度から本格的に改修を進めており、平成30年度には校舎の各フロアに1カ所以上の洋便器を整備した。残された和便器についても継続的に洋便器化を進めている。
本池 トイレ快適化事業でいうと、4年間で37フロア、1年間で10フロア弱しか進んでおらず、212フロア残っていることになる。来年度予算ではトイレ快適化事業計画は3校分で3億1000万円となっており、3校の何フロアが改修されるかは書いていないが、1年間で10フロアずつくらいのペースであれば改修を終えるのに20年くらいかかることになる。「予算を付けているじゃないか」ではなく、実際に必要な改修が必要なペースで進んでいなければ、「お茶を濁している」といわれても仕方ない。洋式化についても計画当初の和便器の数と改修された数を教えてほしい。
藤田教育部長 改修計画時点の和便器の数は2200程度で、令和5年9月時点で文科省が発表している市のトイレの快適化と洋式化を合わせたものは33・6%となっている。
本池 同じ資料によるとまだ2000カ所の和便器が残っている。すべてを洋式化すればいいと思っているのではなく、そのペースを考えてほしい。1フロアに1カ所というのも時代的には少なすぎるし、それに長蛇の列が出来ているのが現状だからだ。今のペースでいいと思っているのか、スピードをあげていきたいのか。
藤田教育部長 トイレ快適化事業は長期間の計画になるため、あわせて和便器の洋式化を進めている。また児童数に合わせた洋便器の整備も必要だと思っている。快適化事業以外についてもしっかり予算を確保してスピードアップして進めていきたい。
本池 今の快適化事業が遅すぎる。トイレも校舎も、これまでの牛歩のようなペースでやっていたのではいつまでたっても改善しない。「下関市政は、子どもの犠牲者が出なければ動かないのだろうか?」という怒りを幾人も学校関係者や保護者の方々から聞いた。
「危険!」「立ち入り禁止」が校内に何カ所もあったり、校舎の廊下に雨漏りを受けるバケツが鎮座する。昨年6月に宮野議員が紹介されたが、安岡小学校のように「要調査」の校舎(要調査とは耐震診断におけるコンクリートの圧縮強度が13・5ニュートン以下のもの、及び耐震補強未実施の校舎)に低学年が詰め込まれ教室不足…。こんな環境をあと何年続けるつもりなのか。圧倒的に予算が足りておらず、危険な状況が刻一刻と進んでいるのが今の学校施設の状況だ。
前田市長に見解を確認
学校施設の老朽化対策にどれほどの予算を割くのか、またどのような方針で進めるのかは、市政全体の判断がかかわる問題だ。前田市長にお聞きする。今の学校施設の状況については説明した通りであり、長寿命化計画でうたっている大規模改修も予防保全も、目の前の危険度を若干軽減させるだけで施設の改善には向かわないことは明らかだ。
なによりまったく間に合っていない。子どもたちの学ぶ環境を改善させるため、小手先の修繕や長寿命化ではなく、必要な校舎については思い切った建て替えが必要と感じているが、建て替えについて早急に検討されないだろうか。
 前田市長 学校施設の保全や改善は、私も大変心配している。8年前に市長に就任し、学校校長会議において小中高全校長の前でも、これまでと次元の違うお金の使い方、安全管理、すべてにおいて責任を持ってやっていくからしっかり声をあげてきてほしいと、最初からいっている。各学校が声を上げてきてくれないと、私が教育委員会に頑張ってやってくれというだけではなかなか進まない。
前田市長 学校施設の保全や改善は、私も大変心配している。8年前に市長に就任し、学校校長会議において小中高全校長の前でも、これまでと次元の違うお金の使い方、安全管理、すべてにおいて責任を持ってやっていくからしっかり声をあげてきてほしいと、最初からいっている。各学校が声を上げてきてくれないと、私が教育委員会に頑張ってやってくれというだけではなかなか進まない。
しかし、この責任を学校に投げるのかというとそうではなく、最終的に足りないところは私の責任であり、私が良くしていくと答えるしかない。
今まで何もしてこなかった下関市だと厳しいことをいわれたが、「これまで何もしてこなかった下関市」ではない。学校トイレも改善しているし、学校のエアコン導入を山口県内で一番早く決断したのは下関だ。そういった頑張ってきたことも入れて、みんなの了解をとるような質問の仕方をしていただきたい。最初に予算を組むというのは配分だといわれたが、正にその通りだ。持っている全部のお金を学校だけにつぎ込んで市政を運営できると思ったら大間違いだ。
あなたはこれまで農業、水産などいろんな質問をされてきたが、その人たちはどうするのか。今回だって物価高騰対策として農家や乳業が大変だから補正予算で2億2000万円を入れた。そういったこともトータルでやっていかないと市政は成り立たない。子どもたちが大切なのはわかる。しかし、みんなが「そうだね、頑張ろう」となるようないい方をした方がいい。学校の子どもたちのことは責任を持ってきちんとやっていく。
本池 市長の討議資料で「加速化」というものを見た。もっと加速化させてほしいと思う。もう一点、市長の討議資料のなかに「旧神田小学校の跡地に最新設備の統合学校建設」とあった。新たな学校施設を整備すること、これは今一番主張していることなので否定はしない。ただ、これに関しては市長の個人的な思いも含まれているかと思う。1校だけ建て替えたとして、残された60校の子どもたちはどうなるのか。長寿命化計画ではそうした部分がまったく見えてこないということをいっている。市のトップとしては、特定の地域のみではなく、市全体のことを考えなければならない。
たしかに、今の学校施設のボロボロの状況は、なにも前田市長の8年間のみで進行したものではない。数十年にわたって後回しにされてきた結果であり、その間に継続してきた長きにわたる下関市政の産物だ。
こうした状況について把握したときに、その時点で市政を預かっている執行部及び市政トップはどう向きあうのか。これが問われているように思う。
前田市政になって確かにトイレなどは進んできた。しかし今のペースを見ているとあまりにも遅すぎる。先ほどいった通り(トイレ改修は今のペースだと)あと20年かかる。これでいいと思っているのか。
今のやり方は、古く危険な施設を残しつつ、他の施策を進めるためにコストがかからないよう時間をかけてちびちびと予算をつけて「やってます」のポーズはしつつ、課題を先送りにしているだけだ。そして学校の老朽化はますます手がつけられないレベルへと向かっている。必要なことに予算をかけるなといっているわけではない。その間に新しいハコモノを建てたり、火の山やあるかぽーとなど、今必要なことなのかと思われる開発事業をどんどんやっておられる。海響館のライトアップに5400万円ついているが、これが遅れたからといって困る市民はほんの一部だ。火の山の山頂トイレは1億1500万円だが、まだ使えるものを壊すくらいなら先に学校の使えないトイレを早急に修繕していただきたい。どう考えても優先順位が違う。そして、大事なことをいわせていただくが、新たなハコモノや開発事業をしていけば次々に維持・管理費が積み重なっていく。結局、新しいものをつくっても維持・管理費をきちんとつけなければ、今起きていることとまったく同じように、後世に負の遺産を残すことになる。
学校についていえば、老朽化すれば当然必要となる維持・管理費は増えるのに、ここ数年の維持・管理費の推移はどうか。ほぼ横ばいかむしろ減少傾向だ。適切な維持・管理費の確保が急がれる。これは学校施設だけでなく、すべての公共施設に通じる課題だ。
今回、子どもたちの教育環境に対し必要な予算がついているのか、もっと大胆につけるべきだという立場から質問した。老朽化した学校の校舎については、既に60~70年も経過しているものを100年使うというような非現実的な計画を抜本的に改めて、思い切った建て替えを最優先でおこなうことが必要だ。早急に計画を立案して事に当たるべきだと考える。そうした学校施設の更新を着実に進め、地元企業も請け負えるような業務として発注していくなら、地域の経済が循環することはいうまでもなく、活性化の一助にもなるはずだ。
新規の、かつ市民に直接関係しないハコモノ行政から一旦立ち止まる勇気をもって、この問題の解決を優先すべきだと思う。なにより下関の子どもたちの教育環境を豊かにするための選択であり、これは次の市長選で誰が市長になろうと避けられない判断であると考える。