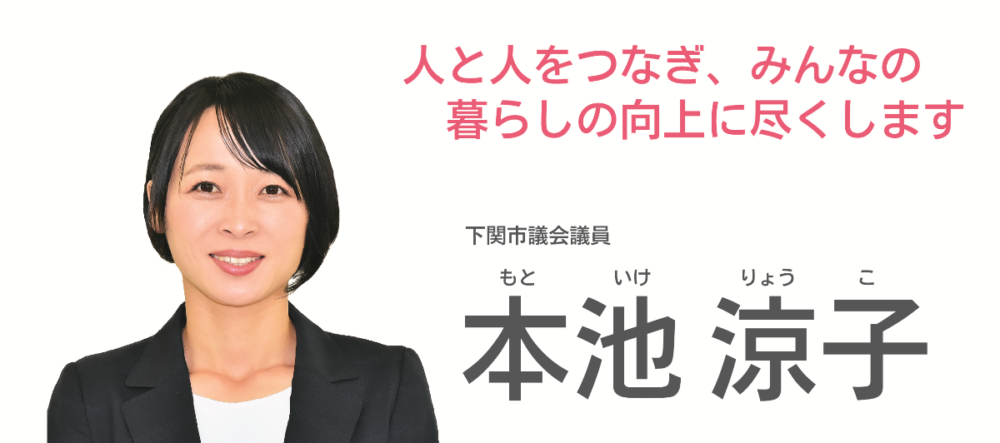本日、令和3年第一回定例会が終わりました。来年度の予算を決める議会なのですが、今年度予算の補正もあり、そのなかに新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る予算が入っていました。すでに医療従事者に対しての先行接種は始まっているのですが、下関のワクチン接種の事業概要をご報告します。
ワクチン接種は全額国費でおこなわれます。予算としては13億4789万円ですが、これはワクチン接種やその準備ににかかるもので、予防接種台帳の改修、接種クーポンの印刷や郵送、コールセンター等の問い合わせ窓口、接種に必要な物資の調達、医療機関との連絡調整や接種費用の支払い等が含まれています。ちなみに市民全員分が確保されており、接種を受ける方は全員無料です。
すでに報道等で明らかになっているとおりワクチン接種の順番は、医療従事者先行接種、医療従事者優先接種(12000人分)、高齢者優先接種、その他(基礎疾患のある方を優先)となっています。使われるワクチンはファイザー製で、2カ所の病院(基本型接種施設:下関では関門医療センターと下関医療センター)にディープフリーザー(超低温冷凍庫)が設置され、そこから「連携型接種施設」や「サテライト型接種施設」となる医療機関に移送される予定となっています。集団接種についての話も出ていますがまだ確定ではありません。ちなみに、高齢者の接種開始が4月中旬ごろの予定のようです。医療機関での接種になるのか集団接種になるのかは未定で、自分で動くことのできない高齢者の方の接種をどうしていくのかも課題です。
市民のみなさんが接種会場に持っていくものは、自宅に届く接種クーポン券と本人確認証の2つということです。(※事前に予約が必要です)
とはいえ、「ワクチンを打ったほうがいいのか」「大丈夫なのか」という声が少なからずあります。ワクチンを打ったあとに発熱等の症状が出る方も少なくなく、海外にいたっては死者も出ていますのでみなさんが慎重になるのは当然です。効果が続く期間についても今のところはっきりわかっていないようで、委員会の場で保健部も「不明」といわれていました。わからないことも多いなかで、ワクチンを打つか打たないかを判断しなければならないということは、自分で判断できる材料が必要です。そうしたものが準備されているのかを質問したところ、全国同一律のものを国に求めているとのことで、それは下関市だけでなく他の自治体からの同じような要求が国に対して上がっているようですので、こちらもまだ決まっていないようです。
時期も場所も方法も不確定ですが、少しずつ決まってる途中ですので、また新しい情報がわかれば発信します。