
9月議会が開会中です。
24日に水道料金の値上げ問題について、一般質問をおこないました。
とりいそぎ、動画でご報告いたします。以下のリンク(議会録画中継サイト)からご覧下さい。
https://shimonoseki.media-streaming.jp/recording/meeting/detail/1178
追って文字起こしを掲載いたします。
声をお寄せいただいた市民のみなさま、傍聴に来ていただきましたみなさま、ありがとうございました。
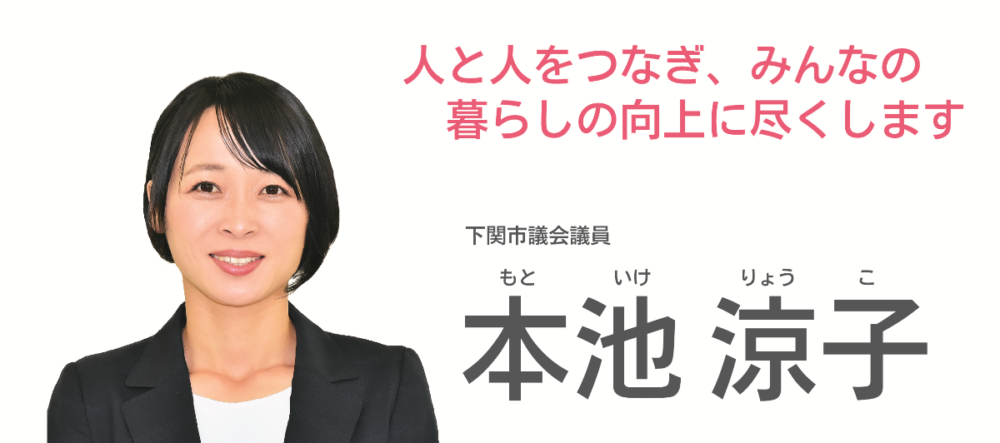

9月議会が開会中です。
24日に水道料金の値上げ問題について、一般質問をおこないました。
とりいそぎ、動画でご報告いたします。以下のリンク(議会録画中継サイト)からご覧下さい。
https://shimonoseki.media-streaming.jp/recording/meeting/detail/1178
追って文字起こしを掲載いたします。
声をお寄せいただいた市民のみなさま、傍聴に来ていただきましたみなさま、ありがとうございました。

下関市議会の6月定例会が始まっています。(6月30日まで)
今議会での一般質問(1人当り50分)は、19~20日、23~24日まで4日間おこなわれます。
私の一般質問の日時は、6月24日(火)の4番目(午後1時ごろからの予定)で、質問のテーマは、固定資産税における船舶特例の適用についてです。
ご都合がつきましたら、ぜひ議場へ傍聴にお越しください。
質疑の様子はネット中継でもご覧になれます→下関市議会HP
下関市議会2月定例会が終わりました。
今回の個人質問では、下関市内の学校校舎がボロボロのまま放置され、子どもたちが危険な状況で学ばなければいけない状況になっていることについて質問しました。さらに、築60~70年を経過した老朽校舎を「長寿命化」によって築100年まで使うという計画も進められています。巨額なハコモノ事業が矢継ぎ早に決まっていく一方で、他市と比べてもあまりにひどい子どもたちの教育環境の現状と今後について、市はどのように考えているのか――。
以下は、私がおこなった個人質問の質疑要旨です。後半では、私の質問に対して前田市長が憤慨される場面もありましたが、こちらが指摘していることとのずれを感じました。その熱量は子どもたちの教育環境改善のために注いでもらいたいと思います。ぜひみなさまのご意見をお聞かせください。

本池 子どもたちが育つ教育・保育環境の維持管理、改修、更新について質問する。この度の予算案は市長選の関係で主に義務的経費や継続事業が計上される骨格予算となっている。であるからこそ、日々必要となる予算が、必要なところに必要なボリュームで宛てられているかどうかを見ることが大事だと思っている。
なかでも今回、下関の将来を担っていく大切な子どもたちが、健やかに、安全に育つ環境になっているか、子育て世代が安心して子どもを預けることのできる施設状況が整っているのか、不具合が生じた場合、適宜改善できる予算が計上されているか。予算議会とは全体の予算の配分を審議するものである。教育費については今年度と比較し10億円の増額となっているが、これが適切な配分であるのか、質問する。
まずはじめに小・中学校の現状について、今、学校関係者、保護者のなかで小・中学校の校舎やその他の学校施設の老朽化が非常に問題にされている。

これは校舎の外壁だ【上、写真】。老朽化した外壁の剥落が起きているため、教育委員会の方が来て危険な箇所を叩き落としているが、ご覧のような状況だ。これが市内各所にある。そして渡り廊下の屋根は、ボロボロになって穴が開いている。
 2枚目は上下とも雨漏りの写真【上、写真】だが、上の写真は屋上のドアの隙間やこの穴から雨が入り込んできて、階段が滝のようになる。下の方は天井が抜いてあり雨漏りの水を受けるバケツが置かれている。3枚目は以前私も一般質問で取り上げたこともあるが、使用禁止のトイレだ【下、写真】。すぐに流せず時間がたてば水が流れてくる「配タンク式」のため、臭いもしやすい。
2枚目は上下とも雨漏りの写真【上、写真】だが、上の写真は屋上のドアの隙間やこの穴から雨が入り込んできて、階段が滝のようになる。下の方は天井が抜いてあり雨漏りの水を受けるバケツが置かれている。3枚目は以前私も一般質問で取り上げたこともあるが、使用禁止のトイレだ【下、写真】。すぐに流せず時間がたてば水が流れてくる「配タンク式」のため、臭いもしやすい。
 今紹介した写真のなかにはすでに改善に向けて進み始めているものも含まれているが、ご覧のとおりあちこちボロボロだ。しかもそれが長期間にわたって放置されていることから、保護者や教育関係者から怒りの声が上がるのも当然だ。
今紹介した写真のなかにはすでに改善に向けて進み始めているものも含まれているが、ご覧のとおりあちこちボロボロだ。しかもそれが長期間にわたって放置されていることから、保護者や教育関係者から怒りの声が上がるのも当然だ。
学校施設の維持・管理については現在、「下関市学校施設長寿命化計画」にもとづき、修繕・工事を実施している。しかしながら、これまで何十年もまともに維持・管理がおこなわれてこなかったため、多くの学校ですでに危険な状態になっている部分も多く、校舎をはじめとした施設の改修・更新が待ったなしの状況だ。他市を経験してこられる先生方、教育委員会関係のみなさんも「下関市の学校施設の古さは異常だ」と話題にしている。
日々学校に通う児童・生徒のために、もっと大々的に、短期間での対策が必要であり、修繕にとどまらず、将来を見据えた思い切った建て替えも必要であると感じている。まず、長寿命化計画による学校施設の維持・管理について、これまでのとりくみを答えてほしい。
藤田教育部長 令和2年度に「下関市学校施設長寿命化計画」を策定し、その後、対象施設等の見直しにともない、令和5年度に改訂した。長寿命化計画にもとづき、学校施設の維持管理を計画的に実施してきているところだ。学校施設の長寿命化のための大規模改修から、外壁落下防止のための外壁改修、漏水対策のための屋上防水改修、水道、電気、ガス管等のライフラインやそれらに関する設備機器類の予防保全、老朽状況等に応じ対応している。
本池 「長寿命化計画にもとづき対応している」といわれたが、先ほど紹介したようにボロボロの状況が長期にわたっていて、今も改修の目途がないものが多くあり、「対応」とはなんなのか考えさせられる。とくに、校内の雨漏りなどは、場所の特定もできずお手上げ状態といわれている。確かに「計画的に進めている」と思うが、対応できているとはいえず、するのであれば劇的に改善する予算を付けなければならない。今の学校施設の置かれている現状を受け、教育委員会としては今後の施設改修の進め方をどのように考えているのか。
藤田教育部長 今後も引き続き、長寿命化計画に基づいて学校施設の適切な維持管理を計画的に実施していきたいと考えている。大規模改修にかかわらず、外壁落下防止等の必要な改修については、その時々に合わせて児童の安全のために計画的に実施していきたい。
本池 あくまでも長寿命化計画にもとづき進めていくということだが、長寿命化計画は、閉校時期が決まっている学校を除き、小・中学校合わせて60校の校舎、体育館、武道場、給食室の254棟が対象となっている。次の図【図1、下】がこの254棟の「築年別整備状況」だが、下関市の場合254棟のうち昭和36年以前に建設された校舎が圧倒的に多いことが分かる。長寿命化に向けて構造躯体の調査をおこない、判定の結果、長寿命化する建物は237棟もある。
 現在、長寿命化改良が進んでいる勝山中学校では3棟の改修がおこなわれており、その期間は今後も含めて7年。残る234棟すべてが完了するのに何年かかるのか。
現在、長寿命化改良が進んでいる勝山中学校では3棟の改修がおこなわれており、その期間は今後も含めて7年。残る234棟すべてが完了するのに何年かかるのか。
この計画には校舎の「目標使用年数」がある。現状の建物の耐用年数は鉄筋コンクリートの場合47年とされているが、長寿命化することで目標使用年数を100年にするという。たった今、今後もこの長寿命化計画にもとづいてやっていくと答えられたが、現場感覚としては100年使うなんてとんでもない話で、早急な改善が求められている。本当に今の校舎群を100年使おうと思っているのか。
藤田教育部長 現在ある建物を今後も長期的に使用する場合の判断として、構造躯体が健全であることが確認できた建物については、必要な改修を実施して引き続き使用したいと考えている。使用できる建物に対して必要な改修をおこない、使用し続けることで総事業費の縮減にも繋がると考えている。文科省においても、平成27年に「インフラ長寿命化計画」を策定し、施設の長寿命化に向けたとりくみを推進しているところだ。ただ一方で、今後、教室の広さや、学習環境に必要な設(しつら)えの変更、また建物構造や安全面の基準等、構造躯体に大きな変更が必要となった場合には、建て替えも視野に入れ検討したい。
本池 今の計画では、構造躯体が健全である建物については改修をして100年使うということか。
藤田教育部長 国の方針もあり、利活用できるものは利活用していく。この計画そのものが事業費の縮減、コストの平準化というのもあり、それらも睨みながら利活用できるものは活用していく。
本池 長寿命化については前提条件があるのだと理解している。確かに国も「100年使える」といっているが、それは適切な管理をしている場合の話ではないだろうか。実際、計画にも「今後は建築後40年を経過するころに改修を実施し、建築後100年まで使用できるよう建物の長寿命化をはかります」とある。
先ほど確認したとおり、下関市の場合50~70年以上たっている校舎が多くある。そしてこれらは「40年を経過するころ」に改修を実施していないどころか、普段の維持・管理もままならず、壊れたり不具合が発生して初めて対応することで現在まできているため、老朽化が深刻になっているのだ。だから、この計画にあるように本当に100年持たせるつもりなのかと聞いている。
そしてみなさん思い出してほしいが、この市役所本庁舎は築59年で建て替えている。建設当時の素材や施工が良かったのか、コンクリートの劣化もさほど進行していないという検査結果も出ていたが新たに建て替えることになった。だったらそれよりも深刻な劣化状況に直面している施設、子どもたちが日々過ごしている学校施設の建て替えの心配をしてほしいし、大人の責任で建て替えてあげなければならないのではないか。市役所だけ建て替えて、子どもたちの使う学校は「躯体が健全だから使えるうちは使う」などあまりにも冷たい。
「建て替えも含めて検討する」といったじゃないかと思われるかもしれないが、今、教育委員会がいっている「建て替え」は、国の施策や方針に対応するためのものでしかなく、下関の置かれている現実からみたボロボロの校舎を早急に改善するための校舎の建て替えは進まない。
20億円かけて大規模改修 なぜ建て替えない?
本池 長寿命化事業のとりくみ内容は「大規模改修」と「予防保全」だ。100年もたせるための大規模改修をおこなっているのが勝山中学校で、令和7年度予算も引き続き勝山中学校の大規模改修にかかる経費が計上されている。勝山中学校の次の大規模改修の計画はあるのか。優先順位第2位となっている川中小学校に着手する見通しはあるのか。 続きを読む