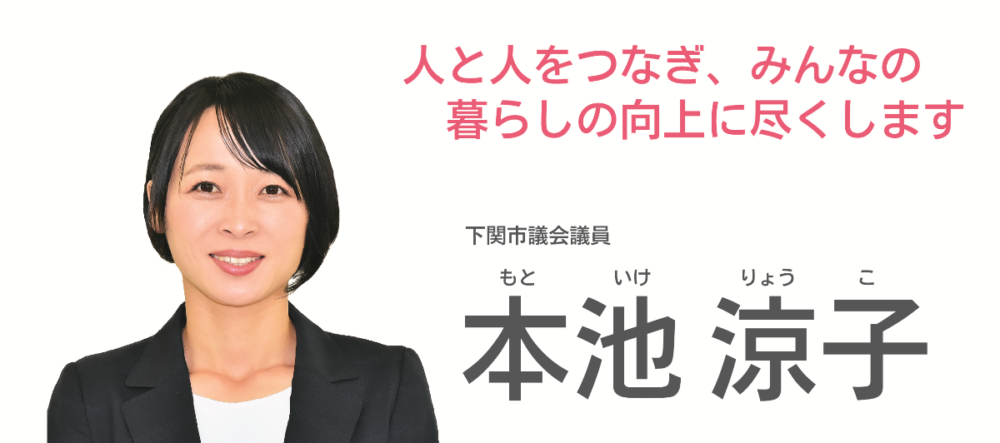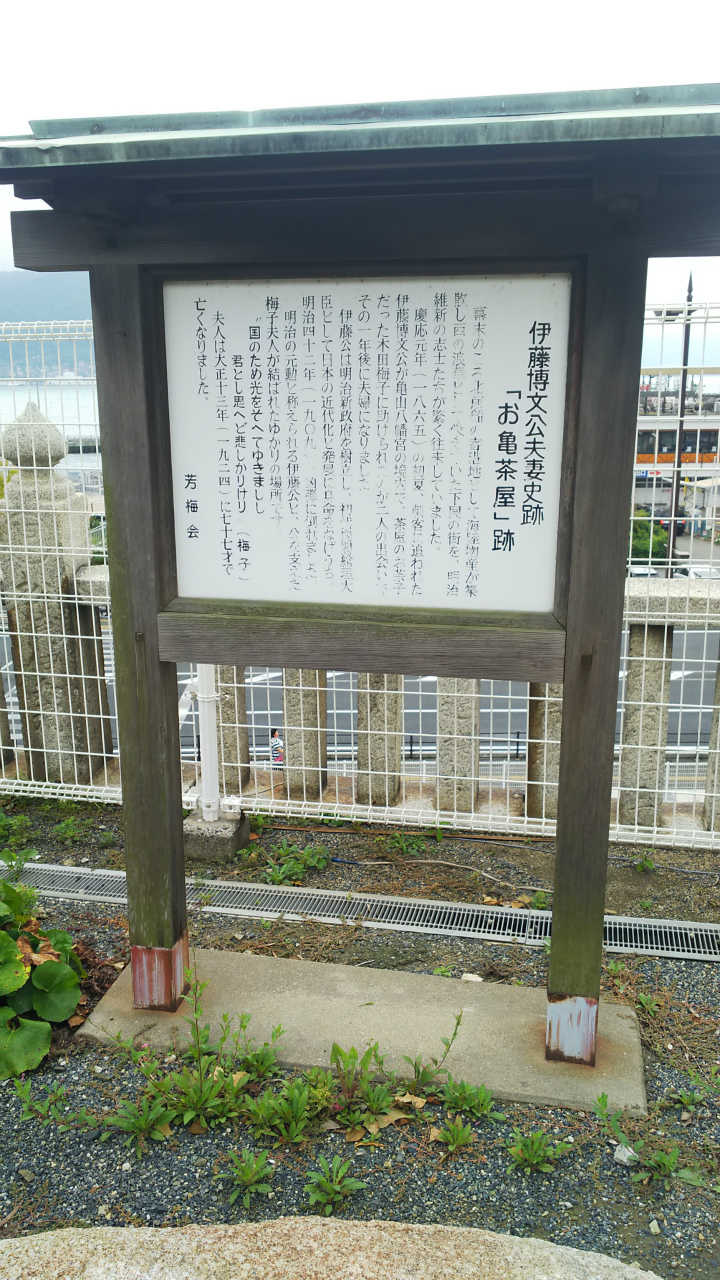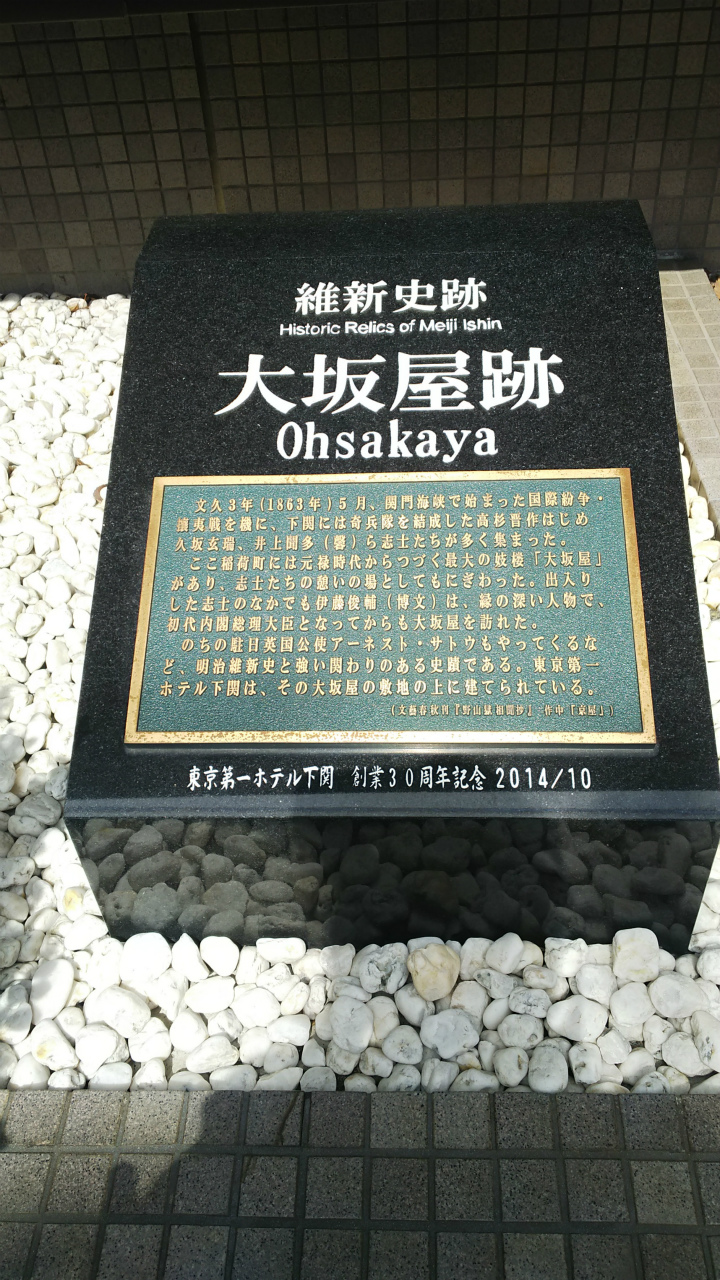10月29日~30日、建設消防委員会の視察で東京に行ってきました。
下関市では総合体育館の建設が予定されており、今の向洋グラウンドの場所が建設候補地となっています。
それも踏まえ建設消防委員会の視察としてPFIで運営している東京スポーツ文化館「BumB(ぶんぶ)」を見学してきました。「ぶんぶ」は、東京江東区夢の島にある体育施設で、昭和30年代のごみ問題をきっかけにできた埋立地に建っています。もとは都営でしたが、平成16年から20年の契約で「PFI区分ユース・プラザ株式会社」が運営しています。同社は大林組やコナミスポーツ、合人社などの企業7社で結成されており、施設内で担当エリアを分けて運営しています。

施設には、スポーツゾーン、文化・学習ゾーン、宿泊ゾーン、パブリックゾーンと4つのゾーンがあります。
写真は、エントランス、メインアリーナ、温水プール、アーチェリーフィールドです。温水プールは、下関と同じでごみ焼却場の余熱施設ですが、少年220円、青年・一般320円とかなり良心的な価格です。
これらの価格は都営時代のものを引き継いでおり、PFI事業になってから独自に変えるということはしていません。自主事業としてスポーツイベントや催しの開催をおこなっているそうです。施設そのものは都のものであることから、当然施設内の設備の改修・更新が必要なときは都に申請しなければなりません。
説明された企業の担当者は、新しいことをやろうと思ってもなかなか自由にできず、時間がかかってしまうことを課題としてあげておられました。事業期間は残り4年。その後については未定だそうです。
企業さんの説明をお聞きして、「結局PFI事業をすることで誰が得をするのか」という疑問がわきました。公共施設や事業をPFI事業で運営することが増えてきて、下関市でも浄水場や新体育館、市営住宅などで設計、建設、運営までを含めたPFI事業計画がつぎつぎに出てきています。行政としては市の負担を少なくすることが目的ですが、それによって公共性が失われ、一部の企業や金融機関がもうけていく仕組みであることはすでに多くの方々が指摘されています。施設や事業によってあらわれかたはさまざまだと思いますが、利用料金が高いか安いか、などといった問題だけでなく、公共施設(事業)としてどうなのか、という視点で今後も見ていきたいと思います。