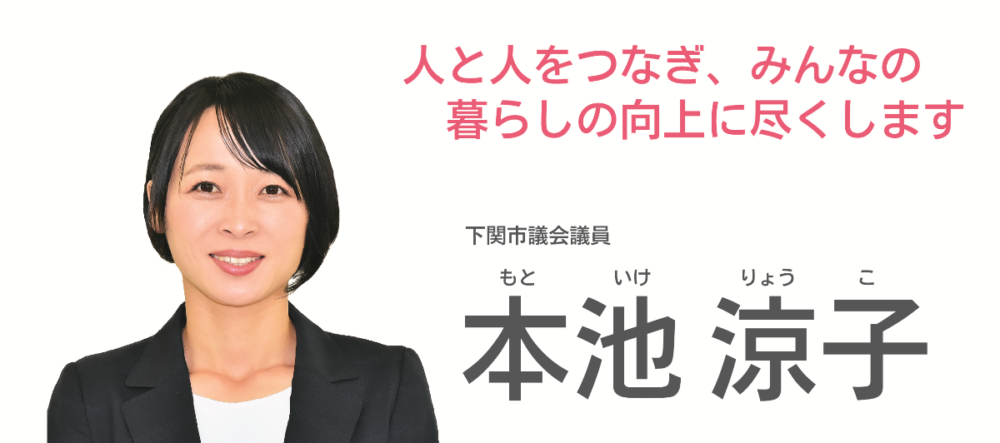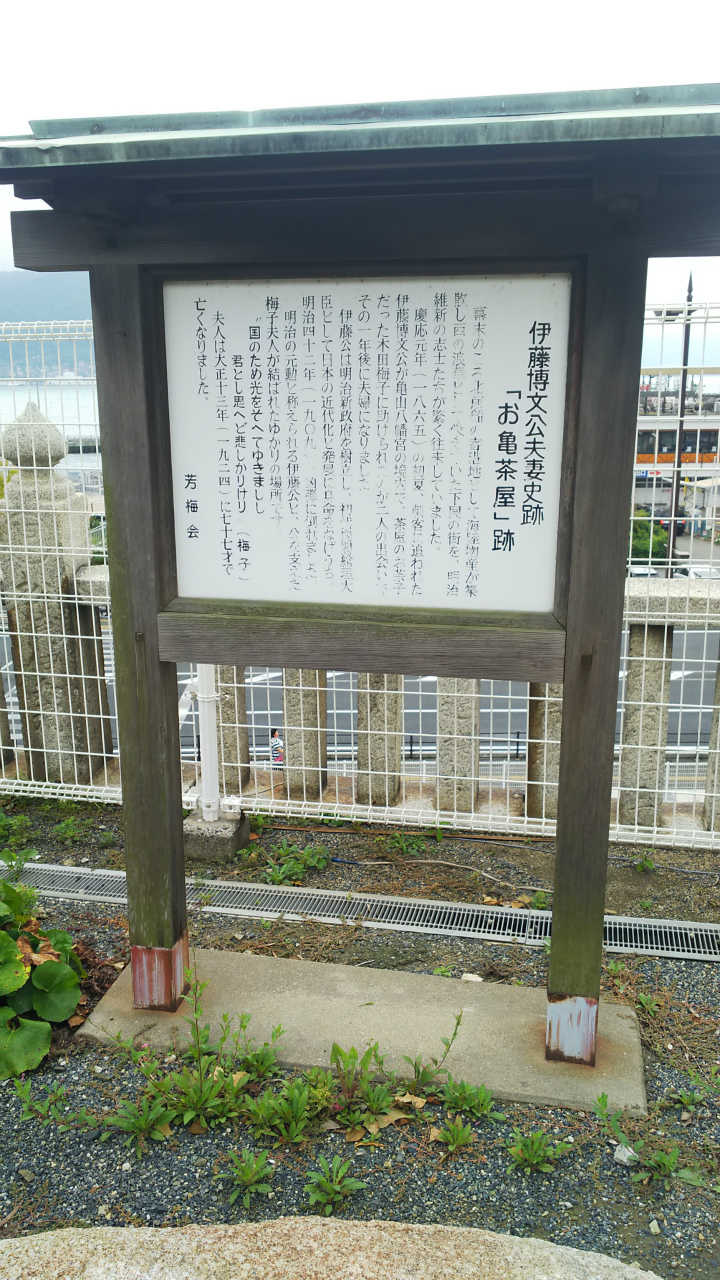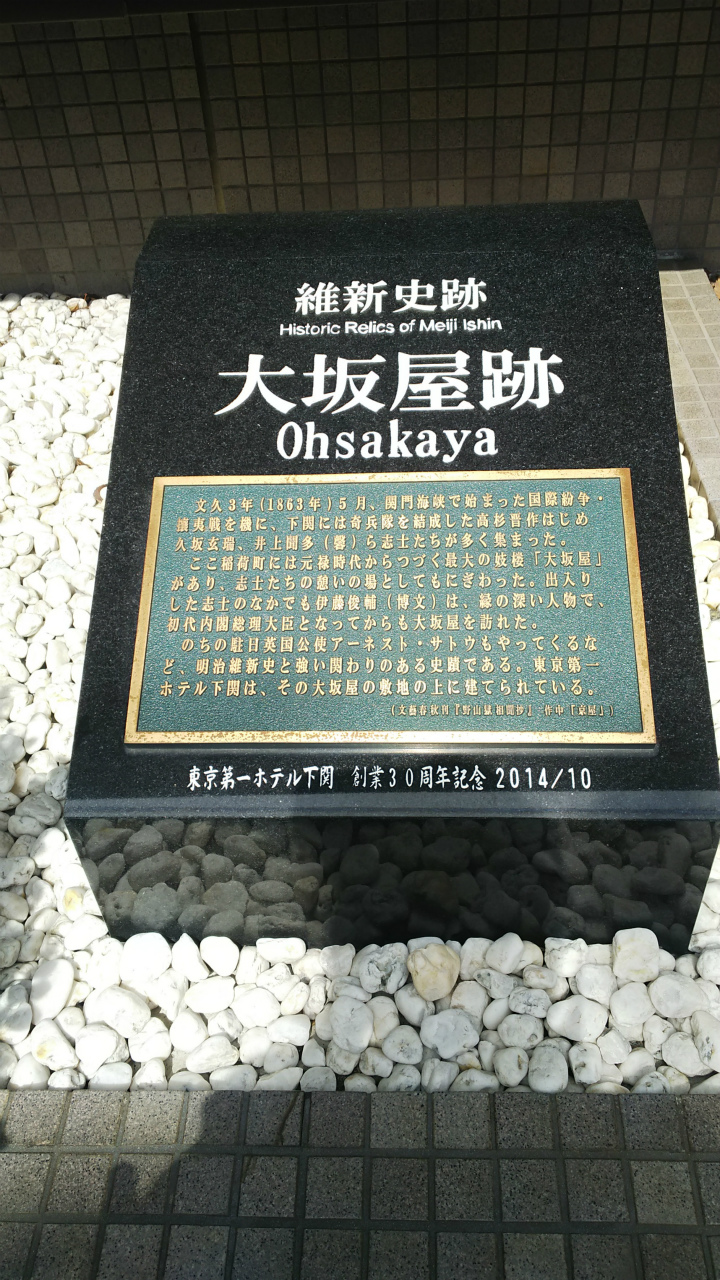本庁と支所に設置してある計画案とパブリックコメント書面提出箱
下関市は10月1日~31日まで立地適正化計画(案)のパブリックコメントをおこなっています。
立地適正化計画は2014年8月に改正・施行された都市再生特別措置法により創設された制度で、国が主導して全国で策定が進められているものです。
都市計画法を中心とした従来の土地利用計画に加え、居住機能や都市機能(商業・医療等)を行政が誘導することで、街の形成や人の流れをつくり、集約型都市構造(コンパクトシティ)に向けたとりくみを推進していくものです。
下関市の計画案では目標年次を20年後の2040年とし、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定しています。対象は、都市計画区域にあたる下関都市計画区域・下関北都市計画区域の二区域となっており、都市計画区域外である豊北町・豊田町はこの計画に含まれていません。
都市機能誘導区域には下関駅周辺と新下関駅周辺を、居住誘導区域には彦島、下関駅周辺、新下関駅周辺、長府、小月、川中、安岡、豊浦、菊川のそれぞれの拠点地域を定めています。誘導するための施策としては、都市機能誘導区域内への都市機能の移転誘導のさいには税制上の優遇策等を検討すること、新規創業の支援を図ることが明記され、居住誘導区域内への誘導も公営住宅の整備、住環境改善、区域外への開発許可制度の見直しなどが盛り込まれています。
立地適正化計画については、計画策定や計画に基づいたとりくみには国から補助金が降りる仕組みになっており、全国の地方自治体が次々に策定しています。
現在、市内あちこちの公共施設が廃止・集約となることが「公共施設等総合管理計画」で決まっていますが、「立地適正化計画」もこれとおなじく国が人口減少のなかでいかに効率的なサービスの提供をおこなっていくかを各自治体に決めさせるものです。財政難の自治体ほど従わざるをえず、人口の少ない農業・漁業地域はますます人が集まりにくく、暮らしにくい地域になっていくことにつながりかねないと思います。
人口減少や低所得化による税収の減少のなかで行財政も大きく変化し、住民サービスをどのように維持していくのかは全国共通問題になっていますが、それによって住民が置き去りにされたり、地域間の格差の拡大が生じることは、本来の行政の役割から見て見過ごすことはできない問題です。
このような市民みんなの暮らしにかかわる重大な問題ですが、現在パブリックコメントの募集がおこなわれていることは市民のみなさまにほとんど知られていません。ぜひみなさまには、自分の暮らしている地域が今後どうなっていこうとしているのか、市全体がどのようになっていくのか、目を通していただき、意見を寄せていただけたらと思います。
「立地適正化計画(案)」のパブリックコメントが閲覧できるのは、本庁仮庁舎の都市整備部都市計画課、豊浦・豊北・菊川・豊田の各総合支所、本庁管内の12支所、そして下関市ホームページです。設置期間は31日までですので、お早めにご覧ください。意見箱と用紙も置いてあります。
「下関市立地適正化計画(案)」について(下関市HP)