

本池 菊川ふれあい会館外壁改修工事について質問する。まず写真を見てほしい。秋ごろから市民の方より「アブニールがひどい状態になっている」というご連絡をいただくようになった。その後私も確認に行きこれは驚かれて当然だと思った次第だ。みなさま「QRコード」とか「日焼けした肌の皮が向けた状態だ」とか表現はさまざまだが、「情けない姿になってしまった」「菊川をばかにしているのか」といった嘆きや怒りの声が寄せられている。なぜ外壁改修工事の後につぎはぎのような状態になったのか、これは設計どおりなのか。
藤田教育部長 設計書にはタイルの色の指定はない。タイルの色は施工時において決定したものだったが、同じ色のタイルがなかった。
本池 では基本的には設計通りで間違いないか。
藤田教育部長 設計書通りだ。
本池 ということは、設計段階でこのようなまだら模様になるということは想定していたのか。
藤田教育部長 設計書にはタイルの色の指定はないので、施工時にタイルを決定し、最終的にこういうタイルはないので、部分改修のさいにはこういうことになることはある程度想定できたが、同じ色合いのタイルを使ったということだ。
本池 想定していたということだ。設計は市が直接されたのか、委託か。
藤田教育部長 設計と工事管理は市がおこなっている。
本池 設計内容はどのようなものだったのか。
伊南建設部長 外壁のタイルが剥落しないよう、まず安全性を第一に優先し、経済性も考慮して部分補修を実施したもの。
本池 この事業の業者決定の経緯(入札状況)について示してほしい。また、その後の請負代金額の変更内容についてもお示しください。
藤田教育部長 条件付き一般競争入札で、当初の契約金額は5390万円だったが、施工前のアスベスト調査でアスベストが検出されため、対策費用の増額により8890万6400円で変更契約を締結している。その後、外壁タイルを撤去し、躯体の劣化調査をおこなったところ、躯体の劣化が確認されたため、8990万9600円で再度変更契約を締結している。
本池 8000万円もかけてこのような状態になったということだ。疑問に思うのは、完成品の検査において検査官がこれを「了」としたのかということだが、これを良しとした理由はなんなのか。
伊南建設部長 検査官の職務にある職員が検査することになっており、工事完了までの施工が設計図書通りにおこなわれているかどうかを検査することになる。検査においては、タイルがしっかり外壁についているか、剥離して落下しそうなタイルを見落としていないかなどを検査している。色合いは検査項目に入っていない。こういった検査の結果、設計図書通りに施工されていたため合格となっている。
本池 今回の設計で求めたことはなにか。
伊南建設部長 タイルがしっかりと外壁についているか、剥離して落下しそうなタイルを見落としていないかということだ。
本池 安全面や危険回避ということなのでしょうが、「安全」と「見栄え」は本来対立するものではないはずだ。安全だったらどんな見た目でもいいのか。論点をすり替えごまかさないでいただきたい。聞きとりのさいは「今後大規模リニューアルもあるかもしれない」といわれていたが、現段階でそのような計画はない。設計図書どおりにできているから「了」としたというが、市民や利用者が見てどうかという評価なり視点を、市役所はもちあわせていないのか。
藤田教育部長 今回のアブニールの関係で、色合いに関していろいろなご意見があることは承知している。ただ、アブニールのタイルが剥がれているということで、これは強風等があればまわりに飛散する可能性もあったので、とくにかく安全性第一に今回は部分改修をしたところだ。当時と同じ色のタイルがあるかというと、なかなか難しいところがあるので、同じ色合いのタイルをしっかり現場サイドで選ばせてもらってやったものだ。決して景観がということではないが、工事の手法としてはこの形で適正にできたものと考えている。
本池 安全はあたりまえだ。そのうえできっちりと見栄えも整え、市民の財産を健全な状態で守っていくのが行政の役割ではないのか。「いや、安全面を優先したのだから見栄えなんてどうだっていいのだ」と開き直ったのでは、8000万円もかけた公共工事から何の教訓も得ることができない。
結果に対して、良くも悪くもその教訓を省みることができない、あるいはしたくないという組織や人間は、また同じことを繰り返すのだろうと思っている。
先ほどの技術職の体制ともかかわってくるが、この外壁問題に関しても「市民の財産」という意識があまりにも感じられない。仮に自分の家の外壁だったらか。今一度アブニールの外壁の写真をごらんになってほしい。「パッチワーク」とか「つぎはぎ」だとか、様々な表現がなされている。一人や二人ではなく、街の話題にされている。そうした方々が先ほどからの部長たちの答弁を聞いてどう感じるだろうか。
本池 アブニールでは日々、多様な講演会やイベント、地域の活動、会議などがあり、令和5(2023)年度は1078件、2万6785人の方が利用されている。教育要覧には「幾世代にわたる交流と賑わいのある中核施設」とされており、まさに菊川町の「顔」といっても過言でない、住民にとって大切な拠点施設だ。それが、蓋を開けてみたらこのような「まだら」な外観になってしまった。そして、市役所内でこれについて、「おかしいではないか」と指摘する人もいない。
前田市長に聞くが、下関の公共施設がこのような状態になっていくことを市長としてどのように考えているか。
前田市長(答弁なし)
藤田教育部長 見栄えをないがしろにしているわけではない。安全性を第一に考えてとにかく早急にやるうえでの今回の手法だ。アブニールは生涯学習施設の拠点として設置しているもの。耐用年数としては50年。さらにいろいろな改修をして大事にしていく施設であるので、教育委員会としても市としても、大事な施設についてはしっかり対応しながら守っていきたいと考えている。
本池 前田市長にお聞きしたい。この前から通告なしの質問に何度も答えられているが、内容によって答えないのか、人によって答えないのか。市長としての見解をお願いする。
前田市長(答弁なし)
藤田教育部長 ふれあい会館は教育委員会所管の施設なので、教育委員会で答えさせていただく。市の施設すべからくそうだが、今回のアブニールに関してもまず安全性を第一にしっかり考えてやった工事だ。工事そのものについては問題ないと考えているし、今示されているようにいろんなご意見があることは承知している。それをしっかり受けとめながら今後に生かしていきたい。
本池 前田市長、答えるか、答えないかお答えください。
前田市長 (答弁なし)
藤田教育部長 あくまで教育委員会所管の施設だ。今回この件に関しては私の方からしっかり答弁させていただきたいと考えている。
本池 前田市長は答えられないということだ。わたしは住民の皆さんからのご指摘を受け、この議場で市の見解を問うた。今の市長の態度も含めて、この外壁工事について話題にされてきた方々に結果をありのままお伝えしようと思う。
たかだか外壁工事というかもしれないが、私はこれは下関のブランディングにもかかわってくる問題ではないかと考える。みなさんブランディングは大好きだと思うのでぜひ耳を傾けてほしいが、住民ですら「なんだ、このつぎはぎだらけの建物は…」と思っている施設に、著名な方や団体も招いて講演会やコンサートがおこなわれ、各地から来られる方々からも「下関の公共施設はつぎはぎだらけだね…」と思われて話題にされる。そんなことも容易に想像がつく。
今、例えば火の山では60億円をこえる壮大な開発計画が進行中だが、一方で、市民が使う施設はつぎはぎだらけ。このような状態を市民のみなさんはどう見るだろうか。安全を優先すれば外観は仕方ないようないい方をされるが、新しい建物についてはむしろ外観しか気にしていないような建築物が今後建てられようとしている。力の入れ方が市民の暮らしや活動でなく、遊び中心、華やかな開発ばかりに傾倒してはいないだろうか。アブニールに関しても、厳密な検証と対応を求める。
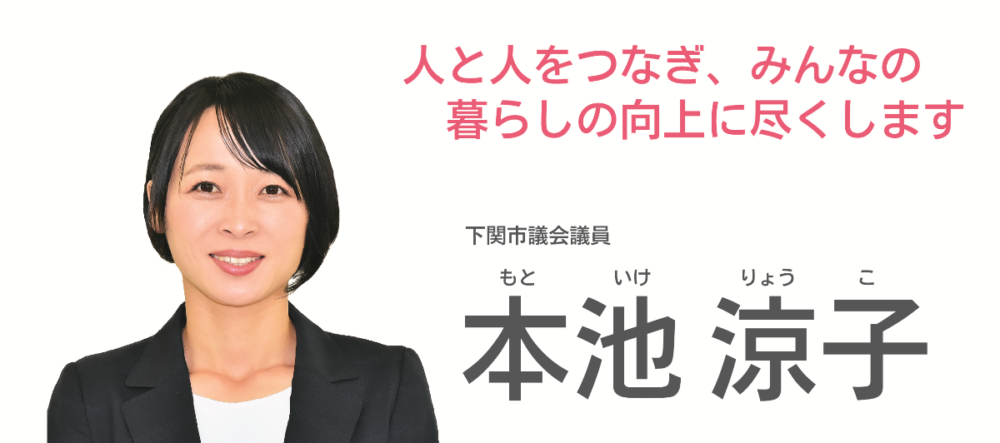

.jpg)
